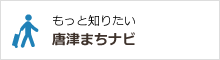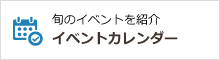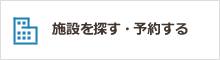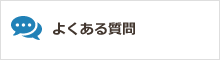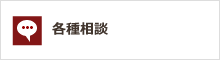ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
国民健康保険の限度額適用認定証などの申請
限度額適用認定証とは
1か月の医療費の支払いが高額となったときは、後日申請することにより所得区分に応じた高額療養費の払い戻しを受けられますが、払い戻しまでの一時的な負担を軽減するために、「限度額適用認定証など(認定証)」があります。認定証を病院や薬局などの窓口で提示することで、医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。
認定証の交付を受けるには、申請が必要です。
交付する認定証は、申請した月の初日(月途中加入の場合は加入日)から利用できます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなく、限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、住民税非課税世帯で過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は、長期の認定申請が必要です。(詳しくは「住⺠税非課税世帯の⼈の⼊院時の⾷事代」を確認してください。)
認定証の種類
限度額適用認定証
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療・食事代を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額されます。
標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)
病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額)が減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額され、食事代(標準負担額)も減額されます。
認定証を提示したときの自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担限度額(1か月あたり)
| 所得区分 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
基礎控除後の所得 901万円を超える |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円] |
|
基礎控除後の所得 600万円を超え901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円] |
|
基礎控除後の所得 210万円を超え600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円] |
|
基礎控除後の所得 210万円以下 |
エ | 57,600円[44,400円] |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円[24,600円] |
- 基礎控除後の所得とは、総所得金額等(給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を引いたあとの所得)から基礎控除額(430,000円)を引いた額です。
- []内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
- 入院中の食事代(標準負担額460円)が令和6年6月1日から490円に増額されます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(1か月あたり)
| 所得区分 |
負担 割合 |
適用区分 |
外来(個人単位) |
入院・世帯単位(外来+入院) |
|---|---|---|---|---|
|
課税所得 690万円以上 |
3割 | 認定証なし |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
|
課税所得 380万円以上 |
3割 | 現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
|
|
課税所得 145万円以上 |
3割 | 現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
|
| 一般 | 2割 | 認定証なし |
18,000円 [年間144,000円] |
57,600円[44,400円] |
|
住民税非課税 (低所得2) |
2割 | 低2 | 8,000円 | 24,600円 |
|
住民税非課税 (低所得1) |
2割 | 低1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 課税所得とは、総所得金額等ー所得控除額(社会保険料、生命保険料などの控除額の合計)を引いた額です。
- []内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
- 所得区分が一般で、年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合は、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
- 低所得2とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の人です(低所得1を除く)。
- 低所得1とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。
- 認定証なしの人は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が認定証の代わりになります。
- 入院中の食事代(標準負担額460円)が令和6年6月1日から490円に増額されます。
住民税非課税世帯の人の入院時の食事代
住民税非課税世帯の人は、認定証を病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額460円)が減額されます。また、療養病床に入院している人は、食事代と居住費の負担がありますが、食事代(標準負担額460円)が減額されます。
70歳未満で住民税非課税世帯の人もしくは70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯(低所得2)の人で、過去12か⽉間の⼊院⽇数が90⽇を超える場合は、入院時の食事代が減額されます。減額を受けるには、⻑期の認定申請が必要です。⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)を持ってきてください。
長期の認定証は、申請した月の翌月の初日から利用できます。
なお、マイナ保険証を利用する場合でも、長期の認定申請は必要です。
入院中の食事代(標準負担額460円)が令和6年6月1日から490円に増額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証を提示したときの食事代
令和6年6月1日から食事代が増額されます。
70歳未満の人
| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 | (90日以内の入院)210円 |
| (90日を超える入院)160円 |
| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 | (90日以内の入院)230円 |
| (90日を超える入院)180円 |
70歳以上75歳未満の人
| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|---|
| 低所得2 | (90日以内の入院)210円 |
| (90日を超える入院)160円 | |
| 低所得1 | 100円 |
| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
|---|---|---|
| 低所得2 |
(90日以内の入院)230円 |
|
|
(90日を超える入院)180円 |
||
| 低所得1 |
110円 |
|
[注]療養病床に入院時の食事代と居住費は、保険年金課または各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。
申請方法
保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請書を提出してください。
- 世帯に税の未申告の人がいる場合や国民健康保険税に滞納があり、国民健康保険通常証が交付されていない場合などは、認定証を交付できないことがあります。
- 70歳以上の住民税課税世帯の人で、課税所得が145万円未満または690万円以上の人(適用区分が低1、低2、現役並み1、現役並み2のいずれにも当てはまらない人)は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が認定証の代わりになりますので、交付申請は不要です。
申請に必要なもの
- 交付を受ける人の国民健康保険被保険者証
- 世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 委任状(別世帯の人が申請するとき)
申請書のダウンロード
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDF:150KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ