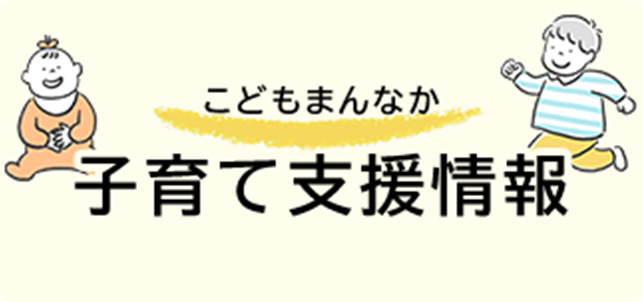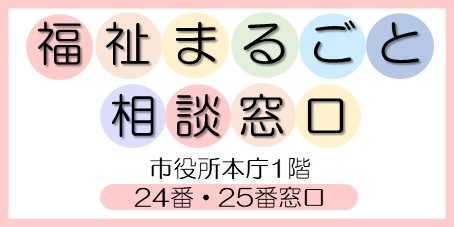本文
食育の推進
食育とは、生きるうえでの基本であって、知育や徳育、体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する力を育むことです。
食育月間と食育の日
食育月間
毎年6月は国が定めた「食育月間」です。食育月間では、国や地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透を図っています。
佐賀県では、県民の皆様の食育への意識を高め、実践を促すために、6月に加えて収穫の時期である11月を食育推進強化月間に定めています。
- 前期…6月(国と同月に設定)
- 後期…11月(実りの秋に設定)
食育の日
毎月19日は国が定める食育の日です。佐賀県では、それに加え、週末にゆっくりご家庭で食育について考えていただけるよう第3金曜日・土曜日・日曜日を食育の日と定めています。
- 農林水産省ホームページ<外部リンク>
- 佐賀県ホームページ<外部リンク>
バランスよく食べよう
主食、主菜、副菜を組み合わせて、栄養バランスの良い食事を意識しましょう。
| 主食 |
ごはん、パン、めん類などを主材料とする料理です。 炭水化物を多く含み、エネルギーのもとになります。
|
|---|---|
| 主菜 |
肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインのおかずとなる料理です。 たんぱく質や脂質を多く含み、体をつくるもとになります。
|
| 副菜 |
野菜、きのこ、いも、海藻などを使った料理です。 ビタミン、ミネラル、食物繊維などを多く含み、体の調子を整えるもとになります。
|
朝ごはんを食べよう
食事を規則的にとり、生活リズムを作っていくことが健康的な生活習慣につながります。
朝ごはんを食べて、脳とからだを目覚めさせ、元気な1日をスタートしましょう。
朝ごはんの役割
- 脳のエネルギー源である糖分を補給して集中力アップ
- 寝ている間に低下した体温が上がり、やる気アップ
- 腸が刺激されてお通じがよくなる
朝ごはんを習慣づけるための3ステップ
ステップ1食べることから始めよう
おにぎり1個、トースト1枚、バナナ1本など、まずは何か食べることから始めましょう。



ステップ2組み合わせてみよう
食べる習慣がついた人は、ごはんやパンにみそ汁や目玉焼きなど2種類以上を組み合わせて食べましょう。





ステップ3バランスよく食べよう
主食(ごはん、パンなど)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品など)、副菜(野菜、きのこ、海藻など)をそろえた食事を心がけましょう。また、牛乳や果物を加えることでさらに栄養バランスが良くなります。