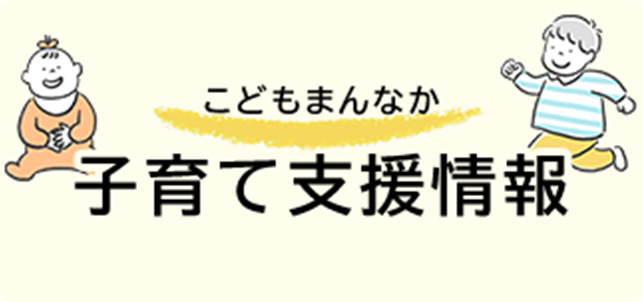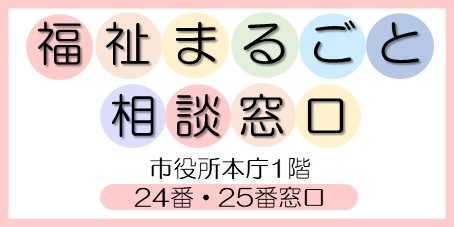本文
水産業活性化支援センター便り~Vol.2
ご挨拶
こんにちは。唐津市水産業活性化支援センターの村山です。
唐津市では平成24年度から九州大学と共同研究で「新水産資源創出研究プロジェクト」に取り組んでいます。
このプロジェクトでは、水産業の活性化と地域の活性化を目指して、相賀の水産業活性化支援センターで、マサバなどの完全養殖技術の開発、ケンサキイカの先端的研究、バイオ水産技術の開発を実施しています。
前回の6月号では、今年度のマサバ種苗生産技術開発について報告しましたが、今回はその続きと、平成26年度に生産したマサバの試験養殖の経過およびケンサキイカのプロジェクトについてお知らせします。
マサバの完全養殖プロジェクト
平成27年度種苗生産技術開発~今年度の試験養殖が始まりました

今年度は、4月下旬から6月下旬にかけて、数回に分けて親魚から卵を採り、飼育を続けています。
このうち最初に卵を採ったグループは、6月上旬に約10cm、重さ11gになった時点で、海のいけすに運び養殖を開始しました。
後のグループも海に出せる大きさになり次第、順次養殖を開始する予定です。これらのマサバは、1年数か月後の来年秋ごろには、出荷可能な大きさに育ちます。
平成26年度生産マサバ試験養殖~大きく育ちました

昨年5月に卵を採って、7月に約7cmから8cmに育てた後養殖を開始したマサバは、今年6月現在で250g前後に育っています。このまま順調に生育すれば、予定どおり秋ごろには出荷できる見通しです。
昨年は出荷間近の8月始めに赤潮の被害をうけ、養殖中のマサバが大量に死んだので、今年は佐賀県の玄海水産振興センターに協力をいただいて赤潮の動向を注視し、細心の注意を払いながら飼育をしていただいています。
先端的研究プロジェクト・バイオ水産技術開発プロジェクト
水産業活性化支援センターでは、マサバなどの魚類の完全養殖技術開発に関するプロジェクトとともに、ケンサキイカの繁殖に関する先端的研究プロジェクトと次世代バイオ水産技術開発プロジェクトに取り組んでいます。
次世代バイオ水産技術開発プロジェクトについては次回以降でご紹介することとして、今回はケンサキイカについてご紹介します。
ケンサキイカの繁殖に関する先端的研究プロジェクト
ケンサキイカについて
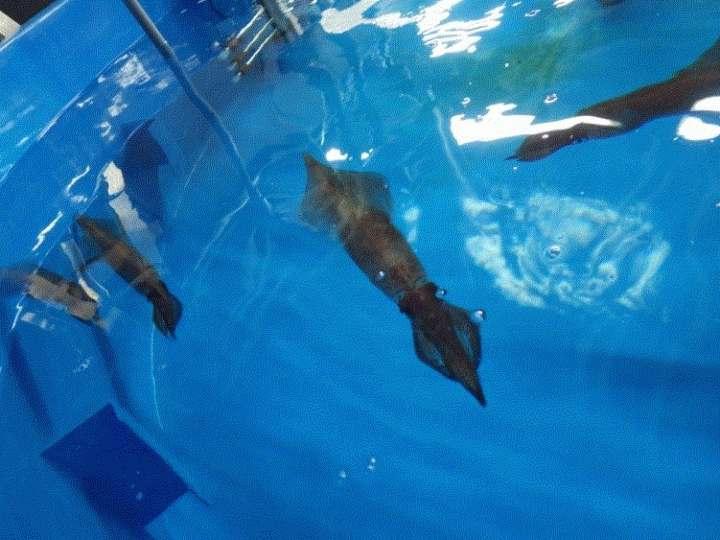
ケンサキイカは呼子のイカとして有名ですが、このケンサキイカをはじめとするイカやタコの仲間では、卵や精子を発達させて産卵に至るまでのメカニズムがほとんど分かっていません。
魚類などの脊椎動物では、脳、脳下垂体(脳の下部にぶらさがっている器官)および生殖腺(卵巣と精巣)それぞれでつくられる様々なホルモンの働きによって、卵や精子が発達します。
その一方で、無脊椎動物のイカやタコなどでは、どのようなホルモンがどこで作られているかが分かっておらず、これがメカニズムの分かっていない大きな原因になっています。
研究内容
そこで当プロジェクトでは先端的な技術を駆使して、卵や精子の発達に必要なホルモンを探索することで、ケンサキイカの性成熟過程を明らかにすることを目標にしています。研究を進めるために水槽の中で性成熟と産卵をさせるための長期飼育技術の開発にも取り組みます。
これらの研究や技術開発により、唐津から世界に向けて学術的に貴重な研究成果の発信を行い、水産都市唐津をPRするとともに、水槽での畜養が難しく、時期によりイカ料理の提供が不安定になりがちなケンサキイカの安定供給も目指します。
用語解説
畜養(ちくよう)
稚魚(ちぎょ)から育てる養殖とは違い、捕らえた魚(主に成魚)を短期間飼育することをいいます。