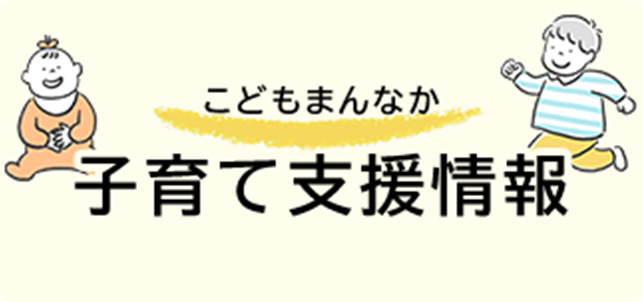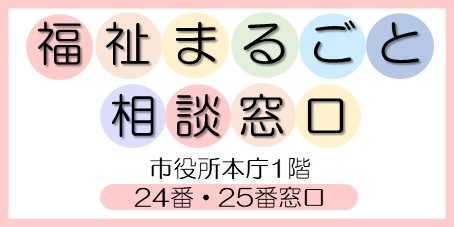本文
年金の種類
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障がいが残ったときのための障害基礎年金、死亡の際の遺族基礎年金などがあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自分で受け取るための手続きが必要です。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上ある人が、原則として65歳になってから一生受けられる年金です。
- 65歳より前に年金を受け取りたい人は、繰上げ請求ができます。繰上げた場合、手続きをした年齢によって年金額が減額され、生涯減額された年金額を受け取ります。
- 65歳より後に年金を受け取りたい人は、繰下げ請求ができます。繰下げた場合、手続きをした年齢が高いほど年金額が増額され、生涯増額された年金額を受け取ります。
障害基礎年金
国民年金加入中や、20歳前の病気やケガによって重い障がいを持ち、日常生活に著しい支障のある人が受け取る年金です。
障がいの程度や保険料の納付要件によって、年金を請求できます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の人や、受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権のある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が請求できます。
生計を維持されていた子とは、18歳の誕生日を迎えたあと最初の3月末日までの子、または重い障がい(障害年金の障害等級1級または2級)のある20歳未満の子です。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた(免除期間も含む)夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
65歳までに再婚した場合は、その時点で権利は消滅します。
死亡一時金と寡婦年金の両方は受け取れず、どちらかひとつを選択します。
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、年金を受けることなく亡くなったとき、遺族基礎年金を受けることができない生計を同じくしていた遺族に支給されます(時効があるため、死亡の翌日から2年以内の請求が必要です)。
寡婦年金を受ける資格がある場合でも、死亡一時金と寡婦年金の両方は受け取れず、どちらかひとつを選択します。
未支給年金
亡くなった人に支払われるはずの年金(未支給年金)が残っていたときに、生計を同じくしていた遺族に支払われる年金です。
年金を受けている人が亡くなったときは、亡くなった月分までの年金が支払われます。
特別障害給付金
学生や主婦は20歳以上でも国民年金への加入は任意でよいとされた時代がありました。
その加入しなかった期間に病気やケガにより、重い障がいが残っても障害基礎年金の請求ができなかった人のため福祉的措置として創設された給付金制度です。
関連リンク
日本年金機構<外部リンク>