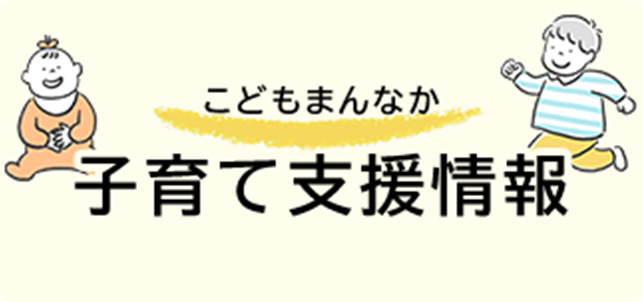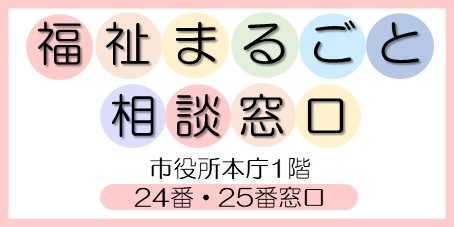本文
打上小学校4・5年生がしめ縄づくり体験(令和5年12月13日、山下定則)

見てください。上手にできました
12月11日、佐賀県唐津農林事務所の『ふるさと「さが」水と土探検支援事業』の第2弾として、打上小学校の4年生13人と5年生22人がしめ縄づくりに挑戦しました。

指導者の紹介
この事業は、体験を通して子どもたちの農業農村に対する理解や興味を深め、ふるさとの農業や自然環境について関心を持つ人になってもらうことを目的に行われました。
今回は、桃山天下市会の「初美の会・しめ縄づくり部会」が協力し、指導をされました。また、この事業のお世話を野崎英信さんが担当されました。

細工しやすいようにたたいて柔らかくします
さあ、しめ縄を作ろうといっても準備が必要です。
「初美の会・しめ縄づくり部会」の皆さんがしめ縄用に準備していたワラをきれいにそろえ、細工しやすいように柔らかくなるまでたたきます。そして、飾りに使うミカンや稲穂、扇や旗もそろえておきます。

ねじって縄を作りますよ
子どもたちがやってきました。作り方を教えてもらい、4人グループを作って作業に取り掛かります。
きれいにそろえられたワラの束を2つに分け、1人が根元をしっかり握り、あとの2人はそれぞれの束をねじり、2つの縄を絡ませます。しめ縄の土台ができ上がりました。その土台に飾りつけをします。

稲穂やミカンを付けました
根元に白い紙を巻き、赤いテープも巻きます。中心付近に稲穂やミカン、「寿」と書かれた扇を刺します。日の丸をつけ、ひもの部分を金色のひもで飾り、出来上がりです。
唐津農林事務所、市民センター産業・教育課の職員さんも初めての体験で大変苦労しながら、楽しんでおられました。

最後にみんなで集合写真の撮影
代表の古舘初美さんは「お正月の縁起物です。ぜひ飾ってください」と子どもたちに呼びかけられていました。
子どもたちも自分が作ったしめ飾りを見て、得意げな様子で持って帰っていました。
(取材地:打上小学校体育館)