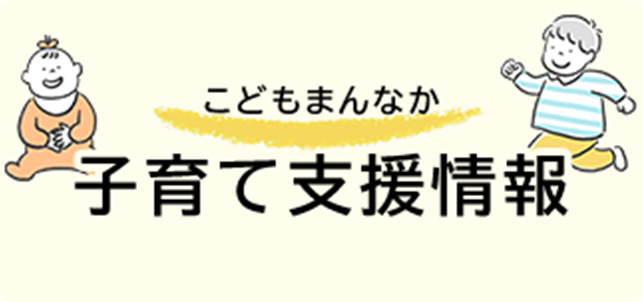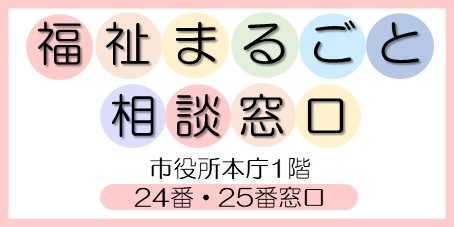本文
駄竹の未来のため元気な海を復活させたい!(令和5年9月5日、井上久美子)

集合写真
8月26日(土曜日)、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で、NPO法人浜-街交流ネット唐津やNPO法人唐津FARM&FOOD、駄竹藻場再生グループなどの協力により、海の中のガンガゼの駆除と藻場の再生について学習会が行われました。

やせ細った藻場
学習会には唐津市内をはじめ、佐賀県内の小学生が参加し、唐津南高生のボランティアやサガテレビのスタッフなど、たくさんの人が駄竹に集まりました。
ガンガゼとは、とげが長い有毒のウニで、海中の岩についた海藻を食べるため、磯焼けの原因となっています。海藻がなくなると、稚魚が隠れる場所がなくなってしまうため、魚が育ちにくくなり、海から魚がいなくなってしまうのです。
かつて駄竹の特産品であったトビウオやサヨリ、カタクチイワシなども、ガンガゼの影響で最近はほとんど見られなくなってしまいました。
海の再生のためには、ガンガゼを駆除するしかありません。地元の漁師の井上勝海(いのうえかつうみ)さん、井上睦健(いのうえよしたけ)さん、井上健一(いのうえけんいち)さんらが集まった駄竹藻場再生グループは、月に1~2回、1回に1,000匹以上を素潜りで捕獲しています。

駄竹藻場再生グループの皆さん
最近は岩の上にいるガンガゼは少なくなりましたが、岩陰に隠れているガンガゼを見つけ出し駆除しなければならず、素潜りではなかなか困難な作業となっています。
捕獲したガンガゼは、身を使ったパスタソースの開発や、殻を使った肥料をミカン農家が利用するなどし、再利用に努めています。
今日のメインイベントは、磯焼けを防ぐための母藻の再生作業です。
参加した小学生が、トウモロコシ製の袋に母藻として、春に成長するワカメ、ホンダワラ、ヒジキ、夏に成長するカジメ、アラメを入れ、海中に沈むよう石も入れました。そのあと船の上から海中へ投入しました。
10日ほどで袋の中から胞子が出て藻になるそうで、藻が成長することで、魚の産卵場所や稚魚の育つ場所ができ、魚が増えていきます。
駄竹藻場再生グループの漁師さんが子どものときにあった、海中には海藻が茂り、岩にはニナやカラスガイがあり、磯遊びをするとサザエやアワビが取れた、そんな海に戻すためにはとてつもない時間が必要です。
ガンガゼの駆除と藻場の再生を駄竹の漁師さんたちは根気強く取り組んでいました。
海が育って漁師になりたい子どもたちが増えることが漁師さんの切なる願いです。
(取材地:肥前町駄竹)