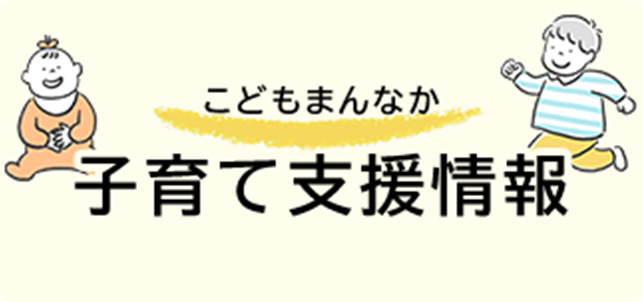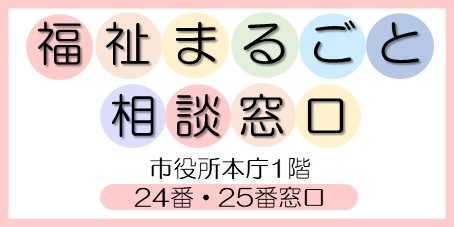本文
貴賤図(御所車)(きせんずごしょぐるま)

画像の無断転用を禁止します。
川村清雄(かわむらきよお) 嘉永5年~昭和9年(1852-1934)
明治31年(1898)頃 油彩・カンヴァス 93.8×159.5センチ
川向こうの行列を、女性と子どもが眺めています。御所車には貴人が乗っているのでしょう、かたわらには7人の従者。はるか山向うに見えるのは京の都の五重塔でしょうか。木々の緑がみずみずしく、美しく水面に映えています。淡くさわやかな色彩で描かれた穏やかな情景は、平安朝の昔を彷彿(ほうふつ)とさせます。油彩で日本的な情緒を表現した画家の代表作のひとつです。
幕末の江戸、ペリー来航の前年に“御庭番”の家筋に生まれた川村は、幼少時より画才を示しました。明治4年(1871)、政治や法律の研究を目的に徳川家の派遣留学生として渡米しますが、周囲のすすめにより翌年画学研究を決意。パリやヴェネツィアで本格的に画技を学び、明治14年(1881)の帰国後は、油彩画の技法に日本画の感覚を融合させ、独自の美意識を盛り込んだ絵を描きました。勝海舟の厚い援助を受けた画家であり、徳川将軍像や天璋院(篤姫)、福澤諭吉らの肖像画を描いたことでも知られます。
川村は、海軍省の仕事をきっかけに、海軍大尉小笠原長生(1867-1958)と知り合いました。長生は、最後の唐津藩主小笠原長国の孫であり、江戸幕府老中小笠原長行の長男です。東京の小笠原邸に滞在した川村は、明治31年(1898)頃に本作を描きました。このとき、日本画家の橋本雅邦と出会い、翌年、日本初の個展といわれる「川村清雄氏揮毫(きごう)油絵展覧会」を東京・谷中の日本美術院で開催することになります。