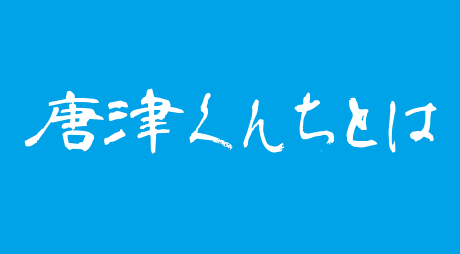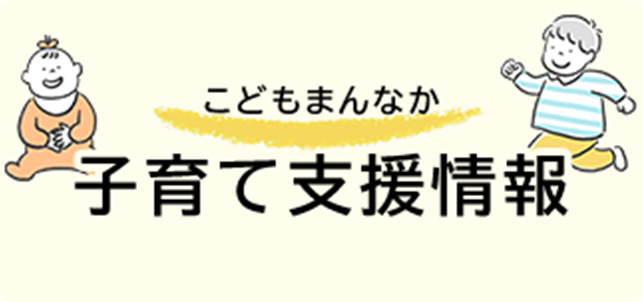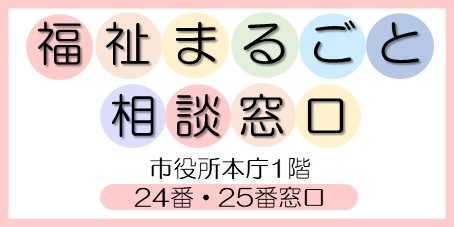本文
曳山紹介
曳山の構造
木組みに粘土で型を作り、その上に和紙を1~3cmの厚さまで100~200枚近くを蕨糊(わらびのり)や渋柿などで張り重ね、型を抜き取り、竜骨を組む。麻布と漆で固めて下地を造り、粉屎漆(こくそうるし)で形状を整え最後に色漆を塗り金箔で仕上げていきます。本体は木製の4輪台車に心柱1本で支えられています。(亀や船型の3台の曳山は心柱2本)製作期間は各町によって差異はありますが、3~6年を要したとされています。
世界最大級の乾漆造(かんしつづくり)の美術工芸品です。
各曳山
1番曳山「赤獅子」

刀町(かたなまち)、文政2年(1819)製作
2番曳山「青獅子」

中町(なかまち)、文政7年(1824)製作
3番曳山「亀と浦島太郎」

材木町(ざいもくまち)、天保12年(1841)製作
4番曳山「源義経の兜」

呉服町(ごふくまち)、天保15年(1844)製作
5番曳山「鯛」

魚屋町(うおやまち)、弘化2年(1845)製作
6番曳山「鳳凰丸」(ほうおうまる)

大石町(おおいしまち)、弘化3年(1846)製作
7番曳山「飛龍」

新町(しんまち)、弘化3年(1846)製作
8番曳山「金獅子」

本町(ほんまち)、弘化4年(1847)製作
9番曳山「武田信玄の兜」

木綿町(きわたまち)、元治元年(1864)製作
10番曳山「上杉謙信の兜」

平野町(ひらのまち)、明治2年(1869)製作
11番曳山「酒呑童子と源頼光の兜」(しゅてんどうじとみなもとらいこうのかぶと)

米屋町(こめやまち)、明治2年(1869)製作
12番曳山「珠取獅子」(たまとりじし)

京町(きょうまち)、明治8年(1875)製作
13番曳山「鯱」(しゃち)

水主町(かこまち)、明治9年(1876)製作
14番曳山「七宝丸」(しちほうまる)

江川町(えがわまち)、明治9年(1876)製作