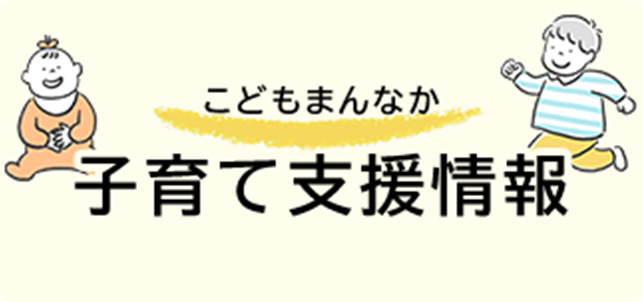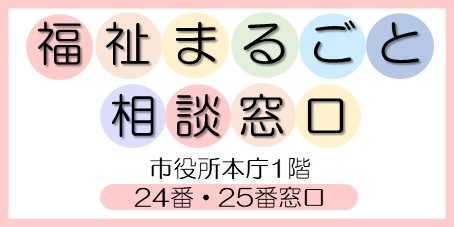本文
産業経済委員会行政視察報告書(令和6年度)
1 参加委員
- 原雄一郎委員長
- 中川幸次副委員長
- 久保美樹委員
- 山下壽次委員
- 黒木初委員
- 進藤健介委員
2 視察日
令和6年5月8日(水曜日)、5月9日(木曜日)
3 視察概要・所感
視察項目1:移住定住支援策について(視察先:鹿児島県薩摩川内市)
概要
市内の8団体(市・商工団体・農協・漁協等)で市の経済問題等を議論し、人手不足・稼ぐ力が課題であると着目し、「薩摩川内E8がんばる宣言」が行われた。プロジェクトチームを設置し、「産業人材確保=移住定住」と捉え「育てる・留める・移り住む」をテーマに、行政機関・経済団体・連携団体に加え、求職者となる小・中・高・大学・教育委員会等も含めた27団体の協議会を設置し、施策を立案された。
本市になく特徴的な支援策として、市内中高生が市内就職時に電子地域通貨が支給される「中高生ふるさと就職奨励金」、市内在住の市内企業正規雇用者に対し奨学金返済が支援される「奨学金返還支援補助金」、転入前後1年以内の中小企業等正規雇用者に対し家賃が補助される「UJIターン者家賃等補助金」、市内在住の高校生等に市内大学等の入学金が補助される「就学定住支援補助金」などがある。
様々な支援策についての効果検証は難しいが、奨学金返還支援補助金については登録者が約190名に対し、年々増加傾向であり一定効果は出ているようだ。
所感
移住定住対策事業も「産業を担う人材の確保」が根本的な指針となっていることから、移住定住対策のターゲットを明確化している点は本市でも参考となる。本市とは経済構造や教育機関等の環境は異なるが、中高生の市外流出および市外流出者の呼び戻しに対し様々な支援がなされており、徐々に効果が表れることが期待される。また、協議会の存在により地元企業や進出企業の情報共有が行われており、教育機関等への情報支援という点でも参考となった。
視察項目2:地域通貨(つんPay)について(視察先:鹿児島県薩摩川内市)
概要
デジタル行政の再構築の一環として、スマートデジタル戦略室にて地域通貨に取り組まれた。デジタル地域通貨の導入経緯は、コロナ禍の商品券発行事業において購入者殺到のトラブルが発生したことにより、事務効率の向上・換金等の人的コスト削減・消費行動の促進を図るため導入された。
デジタル地域通貨のターゲット層として、導入初期にはデジタル化に抵抗が少ない子育て世代に着目し「産後ケア応援券」を発行されている。また、市内旅行者向けに、ふるさと納税の返礼品として「旅トク納税商品券」が発行されている。本年度からは地域通貨の流通促進を図るため、薩摩川内市がSDGs未来都市に選定されていることもあり、SDGsイベント参加や市のSDGs関連事業において地域通貨の交付が行われる。
登録店舗側の負担については、清算処理なども全てシステム処理であるため紙券と比較すると作業負担はほとんどなく、有用と考えられる。登録店舗数は現在約200店あるが、中心地の店舗が多くを占めるなど地域間の偏在があり、登録が少ない地域における店舗数の増加が課題となっている。
システム運用については開発事業者への委託であり、ランニングコストが発生しており、流通額に伴い手数料が加算されていく形式である。今後は市の補助金等を地域通貨で交付するなど安定的にシステム稼働を行い、将来的には商工団体などの民間にプラットフォームを開放し、行政ではできない取り組みなどを含めて運営してもらいたいと考えている。
所感
地域通貨は市内でのみ利用され確実に市内企業に還元されることから、一定の経済効果は見込まれるものの、ランニングコストに対して市民と店舗事業者の双方のメリット創出、流通額を促進させるための行政施策が課題といえる。
本市においても「からふるPay」で使用しているシステムがあり、今後のシステム活用が課題である。薩摩川内市が行うSDGsポイントなどは所管部署の制限が少なく、地域通貨を様々な事業で交付できる手法であり、本市でも様々な取り組みでポイントを交付することができるため、システムの継続的な利用・地域通貨の流通促進・地域経済への還元を行ううえで大変参考となる取り組みである。

視察研修を受ける様子

薩摩川内市議会議場
視察項目3:リノベーションまちづくりについて(視察先:鹿児島県霧島市)
概要
霧島市内の各地域で先進的な取り組みをしている移住者や若者8人を戦略会議の委員に選任し、リノベーションまちづくりを全国的に実施している株式会社リノベリングに事業を委託された。戦略会議で霧島市の強みと弱みを抽出し霧島市のSWOT分析を行い、まちづくり推進ガイドラインが作成された。霧島市のSWOT分析の強みは「都市と自然が共存」、弱みは「遊休不動産が多く、エリアの魅力低下」、機会は「流れはローカル志向」、脅威は「クリエイティブ産業の遅れ」。
事業の内容は、起業などを考える若者たちが交流するイベント、女性起業の推進のために女子起業家スクール、市内の遊休不動産である古民家を題材に3日間で活用方法をオーナーに提案する「リノベーションスクール」などが実施されている。
委託業者である株式会社リノベリングは全国的にリノベーションまちづくりに実績があるため、イベントやスクールが有料でも参加者が集まっている。取り組みの主体は行政・商工団体・まちづくり会社・まちづくりサポーターで構成されるリノベーションまちづくり実行協議会であり、将来的には自立・自走を目指している。
所感
戦略会議の委員には、霧島市内の各地域で先進的な事業や取り組みを行う移住者や若者が選任されており、新たなまちづくりを創造していくうえで、委員の選任は重要なポイントと考えられる。
また、リノベーションまちづくりに実績のある事業者に委託したことにより、しっかりとしたSWOT分析が行われており、制作されたまちづくり推進ガイドラインは読みやすくデザイン性も優れ、若者を引き込む有用な情報媒体となっている。実績ある委託事業者であるため、有料でもイベントやスクールへの参加者が確保できており、委託事業者の選定も重要な要素と思われる。
事業を開始して間もないため目立った結果は出ていないが、この事業をきっかけとした霧島市への移住や新たなイベントが開催されるなど、効果が出始めていると感じられた。本市でも実働部分を民間主導で実施できれば、まちづくりがより活性化されることが期待でき、霧島市の取り組みや行政のサポート方法について、参考にしていきたい。

視察研修を受ける様子

霧島市議会議場