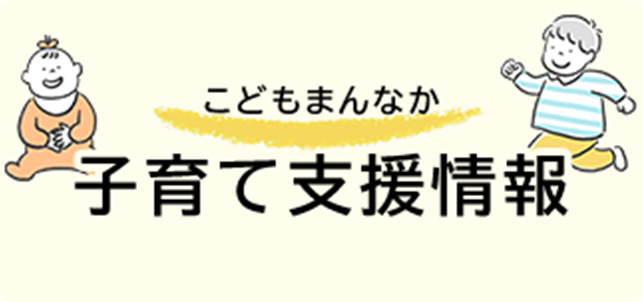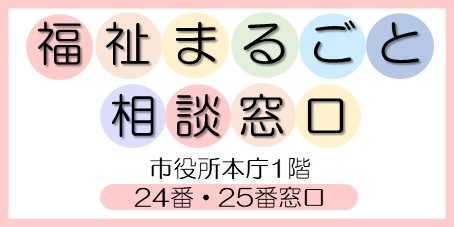本文
総務教育委員会行政視察報告書(令和7年度)
1 参加委員
- 宮本悦子委員長
- 岡部高広副委員長
- 大西康之委員
- 古賀博文委員
- 松本増浩委員
- 楢崎三千夫委員 [注]「崎」の字は、正しくはたつさき(「大」の部分が「立」)
- 田中路子委員
2 視察日
令和7年7月31日(木曜日)、令和7年8月1日(金曜日)
3 視察概要・所感
視察項目1:岡山市DX推進計画について(視察先:岡山県岡山市)
概要
岡山市では、近年のAIやIoTをはじめとするデジタル技術の急速な発展や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として浮き彫りとなった行政のデジタル化の遅れなどを背景として、令和4年3月に岡山市DX推進計画が策定された。
本計画は、全体テーマに『DXによる「住みやすく躍動感のある」まちづくり』を掲げ、デジタル化によって地域経済の発展と市民一人ひとりの幸せをいかに実現するかを課題として捉えたうえで、制度や政策、組織のあり方等も含めた分野横断的な視点の下、(1)地域社会のDX、(2)市民サービスの向上、(3)行政事務の効率化の3つの施策分野について具体的な取り組みや実施時期等を設定されている。
3つの施策分野のうち1つ目の地域社会のDXについては、デジタル技術による企業の生産性向上やイノベーションの創出を進め、オープンデータの推進を図りつつ、地域経済の活性化につなげるとともに、子育てや教育、健康福祉、防災の分野でもデジタル技術を幅広く活用し、市民の安全・安心で快適な生活を実現することを目的に、産業・農業・観光・教育・医療などの分野において個別の目標設定を行われている。この施策分野で実施された具体的な施策例として、IoT・AI等先端技術導入支援補助金や災害避難所の混雑可視化などがある。
2つの目の市民サービスの向上については、行政手続きのオンライン化を推進し、「書かない・待たない」窓口を目指すほか、デジタル技術の積極的な活用により、職員が相談・支援業務などに重点的に対応することが可能となることで市民サービスの向上を目指すものであり、具体的な施策例としては、マイナンバーカードを活用した証明書などのコンビニ交付、AIチャットボットの導入などがある。
3つの目の行政事務の効率化については、全庁的な業務改革を実施して、AI・RPA[注]の導入やペーパレス化を推進するとともに、デジタル人材の確保・育成を図ることにより、将来に向かって質の高い行政サービスを提供し続けるための最適な執行体制を構築することとし、具体的には、音声認識機能を活用した会議録システムの導入や、窓口での会計処理等の業務へのRPA導入などを実施され、いずれも職員の作業時間の削減を達成されている。
また、デジタル人材の確保・育成のため、職員採用試験にデジタル採用枠を設け、民間企業からの人材を積極的に採用するとともに、職員のデジタルスキルアップのため、令和6年2月には岡山市デジタル人材育成方針を策定されている。
[注]RPA(Robotics Process Automation):ロボットによる業務自動化
所感
岡山市の取り組みは、行政内部の業務改善だけでなく、市民サービスの向上や地域課題の解決にもデジタルの力を活用しようとするものであり、DX化を図るうえでは従来のルールを変えることが肝要との説明には感銘を受けた。特に、市民の声、利用者目線を考慮したサービス設計や、デジタルデバイド対策に力を入れている点は、本市においても参考とすべきものである。
また、DX関連予算の予算査定基準がこれまでより柔軟になったこと、デジタル採用枠による市職員の採用、外部専門家の登用や民間企業等との連携・共創にも積極的に取り組まれており、今後、本市においても計画的かつ包括的にDXを推進していくにあたり、体制構築・人材育成・市民との協働など多方面での工夫が必要であると感じた。

視察研修を受ける様子

岡山市議会議場
視察項目2:うちらの避難所登録制度について(視察先:広島県尾道市)
概要
尾道市では、平成30年7月豪雨の際、避難指示が発令され、土砂災害警戒区域などの危険な場所に住んでいるにもかかわらず、避難所に対する不安(避難所を運営する市職員に気を使ってしまうというもの)を理由に避難しない人が多数存在し、その中には単身高齢者も多く含まれていた。
その対応策として考えられたのが「うちらの避難所登録制度」である。
この制度は、自主防災組織等からの申請により、住民が日頃から利用している地域の集会所等を「うちらの避難所」として登録し、風水害時には開設・閉鎖の判断、地域住民に対する開設状況の周知も含め、自主防災組織等が主体となり自主的に避難所を運営するもので、顔見知りの人が運営する身近な施設が避難場所となることで避難所に対する不安を解消し、避難行動を促すことを目的とするものである。
「うちらの避難所」登録の条件は、(1)登録する集会所等が風水害による災害リスクが低いこと(土砂災害警戒区域から外れている、浸水想定区域から外れている等)、(2)風水害時に不特定の地域住民が避難可能なこと、(3)地域住民に「うちらの避難所」に避難するよう周知が可能なこととなっている。
登録された「うちらの避難所」には、市から登録標識を交付され、避難所の運営にあたっては、市から備蓄用毛布や感染症対策用品が支給されるとともに、運営経費として開設24時間ごとに1,000円が補助される。なお、令和6年度時点で登録施設数38件、運営団体数34件となっている。
また、上述した避難所に対する不安解消と合わせて、指定避難所運営に従事する市職員のマンパワー不足を補うために実施されているのが「避難所運営協力制度」である。
この制度は、自主防災組織や町内会等の住民自治組織と市が協定書を締結し、災害時に市が開設を決定した指定避難所の運営を自主防災組織等と市職員が協力して行うものである。
地域住民による避難所の自主運営である「うちらの避難所登録制度」とは異なり、「避難所運営協力制度」は市が指定した避難所の運営であるため、市が作成したマニュアルに沿って避難所運営が行われ、具体的には、避難者の受付、避難者名簿の作成、市への定時報告、備品の設置、毛布や食料などの配布を地域住民と市職員が協同で実施する。
避難所運営に携わった自主防災組織等には、避難所運営協力金として、開設24時間ごとに12,000円が支給される。なお、令和6年度時点で協定締結件数は12件となっている。
所感
尾道市の2つの制度は、単なる避難所運営の効率化にとどまらず、平時からの信頼関係づくりを通じて、災害時の不安軽減とスムーズな避難行動につなげている点、住民と行政の連携による避難所運営が特に参考となった。また、2つの制度を活用している地域の防災訓練には参加者が多い傾向にあるということで、防災意識の向上にも寄与していることは特筆すべき点である。
一方で、島嶼部における災害対応や、高齢者の避難行動、避難所運営における市職員のマンパワー不足など、本市にも共通した課題を再認識することができた。
本市においても、住民と行政による避難所運営協力制度の整備、多様な情報伝達手段の組み合わせと弱者支援の徹底などを図り、それらを拡大・浸透させることで、より強靱で包摂的な防災体制を構築すべきであると考える。

視察研修を受ける様子

尾道市議会議場