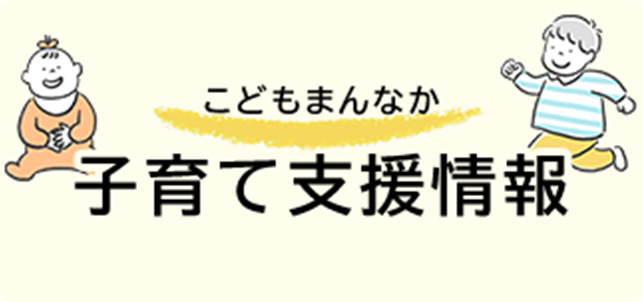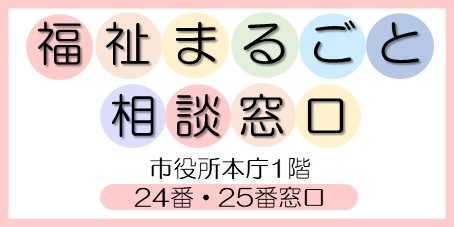本文
意見書(平成28年第4回定例会)
平成28年第4回定例会意見書結果一覧
| 種別 | 番号 | 件名 | 結果 | 提出日 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議決日 | |||||
|
意見書 |
意見書第5号 |
地方財政の充実・強化を求める意見書 |
原案可決 |
10月13日 |
第4回定例会 |
|
10月13日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第6号 |
参議院議員選挙制度における合区の解消に関する意見書 |
原案可決 |
10月13日 |
第4回定例会 |
|
10月13日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第7号 |
食品ロス削減に向けての取り組みを進める意見書 |
原案可決 |
10月13日 |
第4回定例会 |
|
10月13日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第8号 |
「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書 |
原案可決 |
10月13日 |
第4回定例会 |
|
10月13日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第9号 |
男女共同参画基本計画に基づく所得税の見直しを求める意見書 |
原案可決 |
10月13日 |
第4回定例会 |
|
10月13日 |
第4回定例会 |
意見書全文
地方財政の充実・強化を求める意見書
地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定・実行など、新たな政策課題に直面している。
2017年度の政府予算、地方財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積もり、社会保障予算の充実、地方財政の確立を目指すことが必要である。
よって、政府に対し、次の事項の実現を求める。
- 社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
- 子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。
- 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」、「重点課題対応分」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振り替えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
財務大臣 麻生 太郎 様
総務大臣 高市 早苗 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
内閣官房長官 菅 義偉 様
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 石原 伸晃 様
内閣府特命担当大臣(地方創生) 山本 幸三 様
地方財政の充実・強化を求める意見書(印刷用) [PDF/118KB]
参議院議員選挙制度における合区の解消に関する意見書
日本国憲法が昭和21年11月3日に公布されて以来、今日に至るまでの70年間、二院制を採る我が国において、参議院は一貫してその議員の選挙区を都道府県単位とし、地方の声を国政に届ける役割を果たしてきた。
しかし、本年7月10日に憲政史上初の合区による選挙が実施された。
本来、行政区域ごとに集約された地域の声は、各県独自の課題であり、隣県といえども相入れないものも存在している。
こうしたことから、合区により、都道府県ごとに集約された意思が参議院を通じて国政に反映されなくなることは、大きな問題である。
また、今回合区による選挙が行われた選挙区では、投票率の低下や自県を代表する議員が出せないなどの問題が生じている。
我が国が直面する急激な人口減少問題への対応を含め、この国のあり方を考えていく上でも、多様な地方の意見が、国政の中にしっかりと反映されていく必要があることは言うまでもない。
今回の合区による選挙は、あくまで緊急避難措置であり、公職選挙法の附則において、抜本的な見直しが規定されていることからも、早急に課題解消に向けた措置が講じられるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 高市 早苗 様
内閣官房長官 菅 義偉 様
参議院議員選挙制度における合区の解消に関する意見書(印刷用) [PDF/99KB]
食品ロス削減に向けての取り組みを進める意見書
食は世界中の人々にとって大事な限りある資源である。世界では全人類が生きるのに十分な量の食べ物が生産されているにもかかわらず、その3分の1は無駄に捨てられている。中でも、もったいないのは、まだ食べられる状態なのに捨てられてしまう食品ロスである。農林水産省によると、日本では年間2797万トンの食品廃棄物が発生しており、このうちの632万トンが食品ロスとされている。
食品ロスの半分は事業者の流通・販売の過程の中で起き、もう半分は家庭での食べ残しや賞味期限前の廃棄などで発生している。削減には、国民の食品ロスに対する意識啓発が問われてくる。
よって政府においては、国、地方公共団体、国民が一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるため、次の事項について早急に取り組むことを強く求める。
- 学校等における食育・環境教育など、食品ロス削減に効果が見られた好事例を全国的に展開すること。また、食品在庫の適切な管理や食材の有効活用などについて普及啓発を強化すること。
- フードバンクや子ども食堂などの取り組みを全国的に拡大し、未利用食品を必要とする人に届ける仕組みを確立すること。さらに、災害時にフードバンク等の活用を進めるため、被災地とのマッチングなど必要な支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
文部科学大臣 松野 博一 様
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様
農林水産大臣 山本 有二 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
環境大臣 山本 公一 様
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 松本 純 様
食品ロス削減に向けての取り組みを進める意見書(印刷用) [PDF/115KB]
「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書
平成28年6月の佐賀県毎月勤労者統計調査結果によると、佐賀県内の常用労働者数は256,577人、うちパートタイム労働者数は64,837人で25.3%を占める。また、労働者の時間当たりの賃金は、労働者が5人以上の事業所では、一般労働者が1,544円、パートタイム労働者は990円で一般労働者の64.1%と、一般労働者とパートタイム労働者との間で大きな開きがあるのが現状である。
私たちの地域や我が国においても、今後急激に生産年齢人口が減少していく中、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題である。そのためにも、賃金だけでなく正規非正規を問わず社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発及び実施も含めた、雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保がますます重要になっている。そこで、非正規労働者の賃金の見直しやキャリアアップ、さらに正社員転換を視野に入れたワークライフバランスに資する多様な正社員のモデルケースなどの普及も含め、「同一労働同一賃金」の考えに基づく非正規労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施する必要がある。
以上のことより、政府においては日本の独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも十分に留意し、非正規労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる「同一労働同一賃金」の一日も早い実現のために次の事項について躊躇なく取り組むことを求める。
- 不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること。
- 非正規雇用労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正並びに両者の待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて関連法案の改正等を進めること。
- とりわけ経営の厳しい環境にある中小企業に対して、例えば非正規労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするための様々な支援のあり方について実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様
「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書(印刷用) [PDF/129KB]
男女共同参画基本計画に基づく所得税の見直しを求める意見書
2015年に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において所得税法の見直しが盛り込まれた。
これは、地域経済の担い手である中小企業の経営の主力である家族従業員、特に配偶者の果たす役割が大きくその対価を正当に評価しようとするものである。
所得税法では、家族従業員の働き分は事業主の所得となり、配偶者控除86万円、配偶者以外の家族は50万円が控除されるのみで、最低賃金にも達していない。この事によって、社会保障や行政手続きなどの面で弊害が生じている。
青色申告にすれば給与を経費にできるという所得税法第57条は、税務署への届けと記帳義務などの条件付きであり、申告の仕方で納税者を差別するものとなっている。
2014年1月に、全ての中小業者に記帳が義務化されており、所得税法第56条による差別はすべきではない。
第63回国連女性差別撤廃委員会から日本政府に対し、「家族経営による女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と勧告がなされたところである。
いまだに実現していない、所得税法第56条を早急に廃止するよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
財務大臣 麻生 太郎 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
一億総活躍担当大臣 加藤 勝信 様