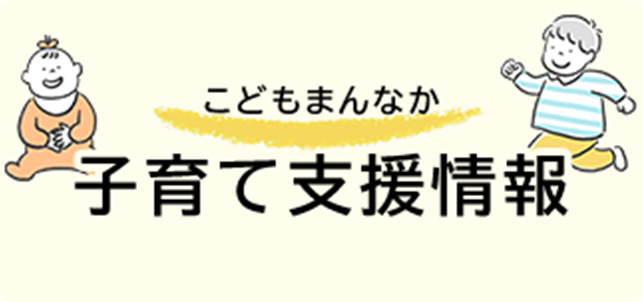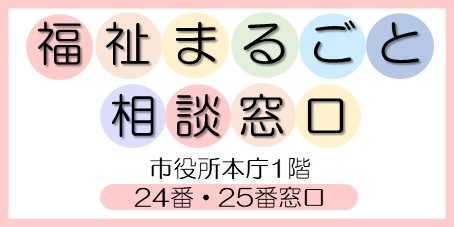本文
意見書(平成30年第1回定例会)
平成30年第1回定例会意見書結果一覧
| 種別 | 番号 | 件名 | 結果 | 提出日 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議決日 | |||||
|
意見書 |
意見書第1号 |
気象事業の整備拡充を求める意見書 |
原案可決 |
3月26日 |
第1回定例会 |
|
3月26日 |
第1回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第2号 |
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書 |
原案可決 |
3月26日 |
第1回定例会 |
|
3月26日 |
第1回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第3号 |
所有者不明の土地利用を求める意見書 |
原案可決 |
3月26日 |
第1回定例会 |
|
3月26日 |
第1回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第4号 |
再生可能エネルギーのさらなる促進を求める意見書 |
原案可決 |
3月26日 |
第1回定例会 |
|
3月26日 |
第1回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第5号 |
子供の医療費等の負担軽減に関する意見書 |
原案可決 |
3月26日 |
第1回定例会 |
|
3月26日 |
第1回定例会 |
意見書全文
気象事業の整備拡充を求める意見書
2011年3月11日に発生した東日本大震災を始めとし、2014年9月27日には戦後最悪の火山災害となる御嶽山の噴火などが発生している。また、2016年4月には最大震度7を2回観測した熊本地震により、阿蘇山付近では斜面崩壊や土石流が発生し、関連死も含めて100人以上の死者を出している。さらに、2017年7月には九州北部で記録的な大雨となり、福岡、大分県で37人の死亡が確認されたのを始め、山・がけ崩れや流木などによる家屋の崩壊、河川氾濫による浸水害など甚大な被害が発生した。こうした相次ぐ自然災害から人命を守るために、更なる防災業務の拡充・強化が求められている。
そのために、基礎となる自然現象の精密な監視・観測を行い、その成果に基づいた迅速で的確な情報を発表することが重要である。また、災害を予防するためには、情報が国民に対してより迅速かつ確実に伝わり、避難などの具体的な防災活動を引き出せるものでなければならない。また、国民全体の気象、地震・火山等の基礎知識や防災意識の向上が、自然災害を軽減するうえで必要不可欠であると考え、気象庁が防災の先頭に立つ国の機関として責任を持って情報の提供・指導をしていくべきだと考える。
これらを実現するため、自然現象の観測監視や、調査研究、数値予報を始め技術開発など、気象庁の基盤となる業務の拡充とそれに必要な要因を確保するよう強く要請する。
- 自然災害から人命を守るため、より精度の高いきめ細かな防災情報が提供できるよう、気象庁の気象観測や予報・技術開発の基盤強化を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月26日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
財務大臣 麻生 太郎 様
国土交通大臣 石井 啓一 様
内閣府特命担当大臣(防災) 小此木 八郎 様
気象事業の整備拡充を求める意見書(印刷用) [PDF/129KB]
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書
欧米を始めとして、先進諸国には協同労働の協同組合が法制度として整備されているが、我が国には法的根拠がないため、企業組合法人や特定非営利活動法人などの法人格を便宜的に活用せざるを得ず、社会的理解が十分に得られない中で事業活動を強いられている。
現在、政府が掲げている「一億総活躍社会」、「地域共生社会の実現」、「まち・ひと・しごと創生」などの課題に答える協同組合組織として、国会では「与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム」、また超党派の「協同組合振興研究議員連盟」において、協同労働の協同組合の法制化に関する検討が開始されている。
働きたいと願う誰もが安心して働ける社会、そしてその働き方が「ディーセントワーク(働きがいのある、人間らしい仕事)」であるような就労機会の創出をめざした法整備を強く求める。
- 持続可能な地域づくりに貢献する「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかなる法整備を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月26日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 野田 聖子 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書(印刷用) [PDF/112KB]
所有者不明の土地利用を求める意見書
平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会・所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積(約720万ヘクタール)に相当する所有者不明土地が発生すると予想している。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べても分からなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるが、探索など手続きに多大な時間と労力が必要となっている。
また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるか不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任するため、不在者が多数に上ると手続きに多大な時間と労力が必要となる。
所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対し、憲法が保障する財産権を侵害しないように配慮しながら、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきである。
- 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。
- 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。
- 所有者不明土地の収用手続きの合理化や円滑化を図ること。
- 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。
- 憲法が保障する財産権を侵害しないよう配慮すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月26日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 野田 聖子 様
法務大臣 上川 陽子 様
農林水産大臣 齋藤 健 様
国土交通大臣 石井 啓一 様
所有者不明の土地利用を求める意見書(印刷用) [PDF/120KB]
再生可能エネルギーのさらなる促進を求める意見書
九州電力株式会社が2014年9月に太陽光発電(家庭の屋根に設置する出力10kW未満の設備を除く)や水力・地熱・バイオマスなど再生可能エネルギーによる発電の新規買い取りを拒否し、北海道電力、東北電力、四国電力、沖縄電力でも相次いで同様の事態が起きた。
電力会社は、電力供給の不安定化を理由にしているが、受け入れが最大どれだけ可能なのか、情報が公開されていない。
この様な中、再生可能エネルギーを推進する政府におかれては、電力会社の再生可能エネルギーの買い取り可能量について、情報公開を求め検証することで、再生可能エネルギーのさらなる可能性が広がるものと考える。
また、政府の審議会(総合エネルギー調査会)の小委員会が行った可能量の試算では、再生可能エネルギーの稼働率を高めに設定していることが、再生可能エネルギーの買い入れ契約の設備量が少なくなっているのも原因の一つとされている。
さらに、FIT法(再生可能エネルギー固定価格買い取り法)によって、電力会社に送電網の増強義務を課す事も重要であると考える。
- 電力会社に再生可能エネルギーの買い取り可能量について情報公開を行うことを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月26日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
農林水産大臣 齋藤 健 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
国土交通大臣 石井 啓一 様
環境大臣 中川 雅治 様
再生可能エネルギーのさらなる促進を求める意見書(印刷用) [PDF/117KB]
子供の医療費等の負担軽減に関する意見書
子供の医療費の窓口負担は、就学前は2割、就学後は3割となっている。子供と保護者が安心して医療機関を受診できるよう、全国の自治体が、少子化対策の一環として更なる減免措置を講じているが、厳しい地方財政では限界がある。
会社員等が加入する被用者保険においては、被保険者の報酬額により保険料が算定されるため、扶養する子供の人数が増えても保険料は変わらない。しかし、国民健康保険は、世帯内の加入者数に均等割保険税が賦課されるため、子供の人数に応じた保険料を負担することになる。
子育ての負担を軽減し、夫婦が理想とする家族構成を実現できるようにするためには、子育て世帯の経済的な負担の軽減に取り組むことが必要である。
よって、政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
- 国民健康保険制度における、子供に係る均等割保険税の負担を軽減すること。
- 国の責任において、更なる子供の医療費助成制度を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月26日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
財務大臣 麻生 太郎 様
総務大臣 野田 聖子 様
厚生労働大臣 加藤 勝信様