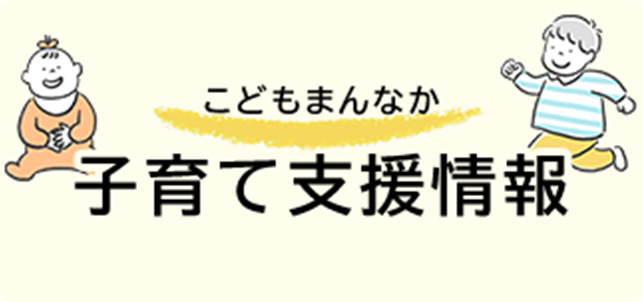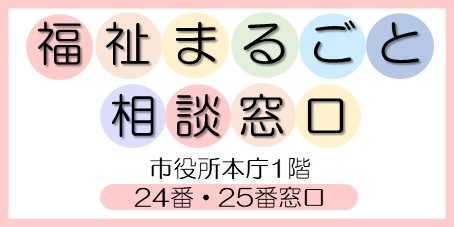本文
意見書(平成26年第4回定例会)
平成26年第4回定例会意見書結果一覧
| 種別 | 番号 | 件名 | 結果 | 提出日 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議決日 | |||||
|
意見書 |
意見書第13号 |
奨学金制度の充実を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第14号 |
森林整備加速化・林業再生基金事業の継続を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第15号 |
手話言語法制定を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第16号 |
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第17号 |
危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第18号 |
産後ケア体制の支援強化を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第19号 |
介護従事者等の人材確保に関する特別措置法を求める意見書 |
原案可決 |
9月24日 |
第4回定例会 |
|
9月24日 |
第4回定例会 |
意見書全文
奨学金制度の充実を求める意見書
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年3%を上限とする利息付の第二種奨学金があり、平成24年度の貸付実績は、第一種が約40万2,000人、第二種が約91万7,000人となっている。
しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加する中、長引く不況や就職難などから、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており、平成24年度の返還滞納者数は約33万4,000人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約925億円となっている。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成24年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入している。さらに、平成26年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど、様々な制限があることに対して問題点が指摘されている。
よって、政府においては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず、安心して学業に専念できる環境を作るため、次の事項について強く要望する。
- 意欲と能力のある若者が、安心して学業に専念できるよう給付型奨学金制度を拡充すること。
- オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に、所得額に応じた返還額を、課税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること。
- 海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力した海外留学支援を着実に実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
文部科学大臣 下村博文 様
奨学金制度の充実を求める意見書(印刷用) [PDF/119KB]
森林整備加速化・林業再生基金事業の継続を求める意見書
森林は、木材の生産はもとより、国土の保全や水源のかん養、地球温暖化の防止など公益的機能を有している。それらの多くは、戦後に造林したスギやヒノキなどの人工林であり、本格的な収穫期を迎えつつある。
一方、地球温暖化が深刻な環境問題となる中で、森林・林業・木材産業を取り巻く状況は依然として厳しく、林業採算性の低下等から、必要な施業が行われず、公益的機能の発揮にも支障を来たすことが危惧されている。
このような状況の中、林業の成長産業化、山村の活性化に向けた取組の推進による森林の適切な維持管理が重要であることから、その実現のためには、木材の生産拡大と利用拡大の両面からの取組が必要である。
本市においては、平成21年度に国において創設された「森林整備加速化・林業再生基金事業」を活用し、地域資源としての森の再生を図る間伐の実施や搬出路網の整備を初め、まつら森林組合の省力化と効率性を高める高性能機械の導入や当地域の材を一括して集約する、からつ木材市場の効率性を高め、流通と加工体制を促進する機械等の導入を行ってきた。
利用策としては市産材を学校、市営住宅へ積極的に活用し、民間の福祉施設においても木の持つ暖かみのある施設整備に取り組むことで、多方面の分野において木材活用の兆しが見え始めたところである。
しかしながら、同事業は平成26年度で終了することとなっており、このまま事業が終了すれば、林業・木材産業のみならず、地域経済に多大な影響を及ぼすことが懸念される。
また、地球温暖化の防止を図るためには、森林整備や木材利用促進などの森林吸収源対策を着実に推進する必要があるが、平成24年に導入された「地球温暖化対策のための税」の使途は、森林吸収源対策には全く充てることができない仕組みとなっている。
よって、森林・林業の活性化に必要な安定的な財源を確保するため、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
- 今後の予算の編成に当たっては、複数年にわたる「森林整備加速化・林業再生基金事業」の継続及び拡充を行うこと。
- 「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を追加すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
財務大臣 麻生太郎 様
農林水産大臣 西川公也 様
経済産業大臣 小渕優子 様
環境大臣 望月義夫 様
森林整備加速化・林業再生基金事業の継続を求める意見書(印刷用) [PDF/138KB]
手話言語法制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
日本政府は障害者権利条約を批准し、すでに成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた「手話」の法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって、国会及び政府においては、そうした環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
厚生労働大臣 塩崎恭久 様
手話言語法制定を求める意見書(印刷用) [PDF/106KB]
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
我が国では、ウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上と言われるほどまん延している。中でも特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎ウイルス感染や集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染については、肝炎対策基本法などにおいて国の法的責任が明確になっている。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業が行われているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼり、本市においても該当する患者が存在し、看過できない問題となっている。
特に、肝硬変、肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
さらに、肝臓機能障害に係る身体障害者福祉法上の障害認定制度は、認定基準が極めて厳しいため、患者に対する実効性ある生活支援には至っていない。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においては、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
よって、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
- 肝硬変・肝がんを含む全ての肝炎医療に係る医療費助成制度を創設すること。
- 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障害認定制度にすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
厚生労働大臣 塩崎恭久 様
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書(印刷用) [PDF/124KB]
危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書
昨今、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(いわゆる「危険ドラッグ」)を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故の事案が度々報道されるなど、深刻な社会問題となっている。
危険ドラッグは「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚せい剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから安易に購入したり、使用したりすることへの危険性が強く指摘されている。
厚生労働省は、省令を改正し昨年3月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入し、成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また、本年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については覚せい剤や大麻と同様、単純所持が禁止された。
しかし、指定薬物の認定には数か月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側で「いたちごっこ」となっている。また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため捜査に時間がかかることも課題とされている。
そこで、政府においては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化することを強く求める。
- インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取締態勢の充実を図ること。
- 簡易鑑定ができる技術の開発をはじめ鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物の認定手続きの簡素化を図ること。
- 薬物乱用や再使用防止のために、「危険ドラッグ」の危険性の周知及び学校等での薬物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
総務大臣 高市早苗 様
文部科学大臣 下村博文 様
厚生労働大臣 塩崎恭久 様
国家公安委員会委員長 山谷えり子 様
危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書(印刷用) [PDF/134KB]
産後ケア体制の支援強化を求める意見書
子育て支援は、国や各自治体の取り組みにより、妊娠・出産・育児と切れ目のない支援策が講じられてきたが、現在、大きな課題になっているのが出産前と直後の対応である。特に、妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要である。
出産により女性の心身には大きな負担が生じる。特に出産直後から1か月間は、身体的な負荷に加えて、急激なホルモンバランスの変化で、精神的に不安定になる傾向が強く、十分な休養とサポートが必要である。
近年、晩婚・晩産により女性の出産年齢が年々高くなってきている。出産する女性の親の年齢も高齢化しており、十分な手助けを受けられない状況がある。また、核家族化が進み、地域との交流も希薄化している中で、不安を抱えたまま母親としての育児がスタートするケースが多くなっている。
良好な母子の愛着形成を促進する上で、出産直後の1か月間が最も大事な時期であり、さらには産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防・早期発見などの役割も果たすといわれている。したがって、出産直後の母親への精神的・身体的なサポートは欠かせないものとなってきている。
国は平成26年度の予算に、これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身をサポートする「妊娠・出産包括支援モデル事業」を計上した。少子化対策を進めるに当たって「産後ケア対策」は喫緊の課題であり、早急に確立する必要がある。
よって、次の事項を実現するよう強く求める。
- 「妊娠・出産包括支援モデル事業」を着実に実施すること。その上で、本事業の成果を速やかに検証し、全国の自治体で円滑に産前・産後の支援、特に産後ケアを提供できる体制を構築すること。
- モデル事業の展開に当たっては、経済的な理由により、産後ケアが受けられないことがないよう、利用者負担軽減策を同時に実施すること。
- 単なる家事支援ではなく、出産後の母子のこころとからだの適切なケアが提供できるよう、産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
厚生労働大臣 塩崎恭久 様
産後ケア体制の支援強化を求める意見書(印刷用) [PDF/122KB]
介護従事者等の人材確保に関する特別措置法を求める意見書
政府は介護職員を2025年までに、現在より100万人増やすことが必要だとしている。
しかし、介護労働者が依然として他産業に比べて賃金が低く、厳しい労働環境に置かれていることが人材確保につながらない結果となっている。
今年4月、衆議院本会議において野党6党共同提出の「介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案」が審議入りした。
しかし、福祉人材の確保という国民にとって重要な法案であったにもかかわらず、継続審議とされた。
介護従事者等が他産業従事者と比べて低い賃金に置かれている問題を放置したままでは、問題の深刻化に一層の拍車をかけることは必至である。
よって、国が介護保険制度の改善や交付金などで、介護・障害福祉従事者の処遇改善に取り組むことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
財務大臣 麻生太郎 様
厚生労働大臣 塩崎恭久 様