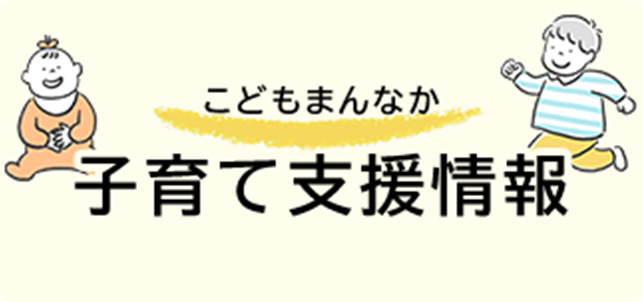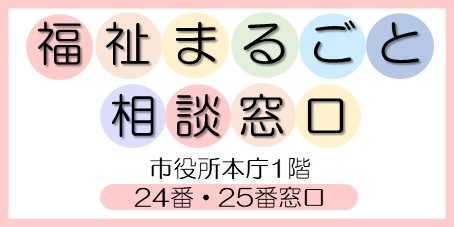本文
意見書(平成26年第3回定例会)
平成26年第3回定例会意見書結果一覧
| 種別 | 番号 | 件名 | 結果 | 提出日 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議決日 | |||||
|
意見書 |
意見書第7号 |
参議院選挙制度改革に対する都道府県単位の制度を堅持することを求める意見書 |
原案可決 |
6月24日 |
第3回定例会 |
|
6月24日 |
第3回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第8号 |
電源立地地域対策交付金等に係る交付地域拡大に関する意見書 |
原案可決 |
6月24日 |
第3回定例会 |
|
6月24日 |
第3回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第9号 |
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 |
原案可決 |
6月24日 |
第3回定例会 |
|
6月24日 |
第3回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第10号 |
中小企業の事業環境の改善を求める意見書 |
原案可決 |
6月24日 |
第3回定例会 |
|
6月24日 |
第3回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第11号 |
若者雇用対策の拡充と安定した雇用を求める意見書 |
原案可決 |
6月24日 |
第3回定例会 |
|
6月24日 |
第3回定例会 |
||||
|
意見書 |
意見書第12号 |
TPP(環太平洋連携協定)交渉に国会決議を遵守する態度を求める意見書 |
原案可決 |
6月24日 |
第3回定例会 |
|
6月24日 |
第3回定例会 |
意見書全文
参議院選挙制度改革に対する都道府県単位の制度を堅持することを求める意見書
参議院の「一票の格差」是正に向けて選挙制度改革を検討する「選挙制度協議会」の会合が4月25日に開かれ、その中で脇座長は、人口の少ない県を隣県と合区する案を提示された。
最高裁判所が違憲状態とした一票の格差を是正しなければならないことは当然であるが、最高裁判決が参議院の格差のない比例票や半数改選などの特色を考慮せず、機械的に格差2倍以内に収めることを求めているとは一概には言えない。
脇座長案では、佐賀県選挙区は福岡県選挙区と合区し、定数自体は維持する案となっているが、福岡県の人口は佐賀県の6倍で、佐賀県から代表を参議院に送ることが極めて困難なことは明白である。
人口の少ない県こそ政治の力が必要であり、加えて、一票の格差問題は人口を基に論じられているが、一票の価値は、実際に投票された数を基準に考慮すべきとの考え方もある。
参議院においては、都道府県単位を極力維持するなど地方の声が国政に届く選挙制度となるよう慎重に議論されることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
参議院選挙制度改革に対する都道府県単位の制度を堅持することを求める意見書(印刷用) [PDF/96KB]
電源立地地域対策交付金等に係る交付地域拡大に関する意見書
今日の我が国において、エネルギーの安定的な確保は、国民生活と産業活動に不可欠なものであり、常に大きな課題である。このような状況に対応するため長期的、総合的かつ計画的な視点に立って、エネルギー政策の推進が図られているところである。
エネルギー政策を円滑に推進する上で、特に原子力発電については、電源地域との理解と協力は不可欠なものであると考えるところである。国においては、平成26年4月11日に新しいエネルギー基本計画が閣議決定された。
これまでも原子力発電所の隣接自治体である唐津市においては、原子力発電所の安全確保を大前提として、諸問題を解決しつつ、この政策に対応してきたところである。
原子力発電所の周辺市町村に対しては、電源立地地域対策交付金等の制度が設けられ様々な助成がなされており、この中で隣接市である本市においては、電源立地地域対策交付金(給付金交付助成措置)及び電源地域振興促進事業費補助金(原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業)が該当するところである。
本市は、平成17年、平成18年に合併し新しく誕生したが、その制度の対象地域は、合併前の地域のままであり不均衡な状態となっている。
対象地域の拡大については、平成18年にも唐津市議会として是正を求め、意見書を提出してきたところであるが、いまだ改善されず、合併後10年が経過し、全市が一体となった均衡ある発展を目指す唐津市にとっては、対象地域が全地域となることを強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
財務大臣 麻生太郎 様
経済産業大臣 茂木敏充 様
電源立地地域対策交付金等に係る交付地域拡大に関する意見書(印刷用) [PDF/109KB]
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書
現在、国においては義務教育制度の35人以下学級について、小学校1年生、2年生と続いてきた35人以下学級の3年生以上の拡充が予算措置されていない。日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。
全国の多くの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による30人~35人以下学級が行われている。このことは、自治体の判断として少人数学級の必要性を認識していることの現れであり、国の施策とすべき必要がある。また、文部科学省が実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26人~30人を挙げている。国民も少人数学級を望んでいることは明らかである。
また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられた。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員も増えている現状である。
将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要である。未来への大事な先行投資として、国の財政を割いて子どもや若者の学びを切れ目なく支援し、人格の完成、人材育成、雇用・就業の拡大につなげる必要がある。
こうした観点から、2015年度政府予算編成において次の事項が実現されるよう要望する。
- 国の政策として、少人数学級を推進すること。
- 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を2分の1に復元すること。
- 学校施設整備費、就学援助・奨学金など教育予算の充実のため、国の予算を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月24日
佐賀県唐津市議会
衆議院議長 伊吹文明 様
参議院議長 山崎正昭 様
内閣総理大臣 安倍晋三 様
財務大臣 麻生太郎 様
総務大臣 新藤義孝 様
文部科学大臣 下村博文 様
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書(印刷用) [PDF/120KB]
中小企業の事業環境の改善を求める意見書
今年の春闘の大手企業からの回答では、13年ぶりに全体の賃上げ率が2%台となったが、景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然厳しいといえる。さらに、消費税8%引き上げに伴う駆け込み需要の反動減も今後予想され、対応策を講じなければならない。
国際通貨基金(IMF)は3月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げを「アベノミクス」の課題として挙げている。実質的には、企業の収益力次第で賃上げの可否が左右されてしまうため、政府が掲げる「経済の好循環」を実効的なものにするためには、中小企業の収益力向上につながる事業環境の改善が求められる。
今後も経済成長を持続的なものにするため、成長の原動力である中小企業が消費税増税や原材料・燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目のない経済対策が必要である。政府においては、地方の中小企業が好景気を実感するため、次の事項について対策を講じるよう強く求める。
- 中小企業の“健全な”賃上げ、収益性・生産性の向上に結び付くよう、経営基盤の強化策及び資金繰り安定化策を図ること。
- 「小規模企業振興基本法案」を軸に国・地方公共団体・事業者の各責務の下で、円滑な連携と実効性が高まる制度設計を図ること。
- 中小企業・小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促すよう、キャリアアップ助成金などの正規雇用化策を更に周知するなど、従業員の処遇改善を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月24日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎 様
厚生労働大臣 田村憲久 様
経済産業大臣 茂木敏充 様
中小企業の事業環境の改善を求める意見書(印刷用) [PDF/127KB]
若者雇用対策の拡充と安定した雇用を求める意見書
若者を取り巻く雇用環境は、非正規労働者の増加の中で、中小事業者における離職率の高さや、若年層を恒常的・大量に雇用し、低水準・過酷な労働条件で労働を強いる「使い捨て」問題や、180万人といわれるフリーターや60万人のニートの問題など、雇用現場における厳しい状況が続いている。
また、我が国は、働く者のうち約9割が雇用労働者であり、雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。
政府においては、わかものハローワークや新卒応援ハローワークなどにおける支援や、「若者応援企業宣言」事業、労働条件相談ポータルサイトの設置、地域若者サポートステーションにおけるニート対策などに取り組まれているが、それぞれの事業の取り組みが異なっており、関係機関において必ずしも有機的な連携が取られている状況ではない。
安倍政権における経済対策により、経済の好循環が始まる中、新規学卒者の内定状況も好転し、賃金上昇に取り組む企業が出てきているが、唐津市においては、有効求人倍率が佐賀県の有効求人倍率を上回るなど景気の回復の兆しが見られるものの、正規雇用の拡大や賃金の引き上げについては、まだ厳しい状況である。
改めて、若者雇用対策を総合的かつ体系的に推進するための仕組みを構築するとともに安定した雇用の実現のため、政府においては、次の事項について対策を講じるよう要望する。
- 若者雇用に係る総合的、体系的な対策を進めるため、若者雇用対策新法を制定し、若者本人を支える家庭、学校、地域、企業、国・地方の行政の責務を明確にし、緊密に連携して支援を行える枠組みを整備すること。
- 「若者応援企業宣言」事業について、中小企業等の認定制度として拡充し、認定企業の支援措置を新設すること。また企業が若者を募集する際の情報開示を促す仕組みをつくること。
- 大学生等の採用活動後ろ倒しに伴い、新卒応援ハローワークにおける支援措置を強化すること。
- 若者が主体的に職業選択・キャリア形成ができるよう、学生段階からのキャリア教育の充実強化を図ること。
- ニート等の若者の孤立化を防ぎ、自立に向けた充実した支援を行うことができるよう地域若者サポートステーションの機能の強化を図ること。
- 派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。
- 雇用・労働政策に係る議論は、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行われるべきであること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月24日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
文部科学大臣 下村博文 様
厚生労働大臣 田村憲久 様
若者雇用対策の拡充と安定した雇用を求める意見書(印刷用) [PDF/141KB]
TPP(環太平洋連携協定)交渉に国会決議を遵守する態度を求める意見書
農林水産業で生計を立てる生産者は、政府が交渉するTPPの分野において地域社会を崩壊させる問題点が多いと不安を抱いている。これまで、国会決議を遵守できない問題が生じれば、撤退すべきであるとの要求を常に重ねてきた。
日米二国間の物品市場アクセス交渉や自動車協議の動向が交渉全体の鍵を握るとされる中、4月24日に日米首脳会談が開催されたが、大筋合意に至らず、引き続き協議を継続することとされた。
日米共同声明においては、「TPPに関する二国間の重要な課題について前進する道筋を特定した」と明記され、これを受けて安倍総理はTPP交渉全体を早期に妥結させるとの意欲を示すなど、交渉の先行きについては依然として予断を許さない状況が続いている。
唐津市議会は、引き続きTPPが日本の食と暮らし・いのちの危機に通ずるような交渉には強い姿勢で臨み、農林水産業の崩壊にならないよう強く求めるとともに、交渉に関する情報開示を徹底し、今後の交渉が国会決議に反するものならば撤退も辞さない覚悟で交渉に臨むよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月24日
佐賀県唐津市議会
内閣総理大臣 安倍晋三 様
財務大臣 麻生太郎 様
農林水産大臣 林芳正 様
経済産業大臣 茂木敏充 様