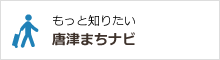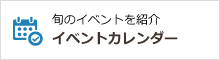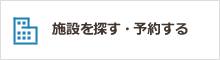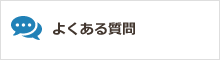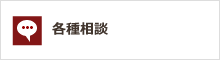ここから本文です。
更新日:2024年3月12日
第7期からつ自立支援プラン(案)についての意見
意見募集結果
| 意見募集期間 | 令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで |
|---|---|
| 意見提出者 | 2人 |
| 提出方法 | 窓口:1人、ファクス:1人 |
公表した案など
住民からの意見
日中活動系サービス【就労移行支援】「実績の評価・課題及び第7期の見込み量について」(計画案29ページ)
意見の趣旨
「令和3、4年度はサービス提供事業所が少ないこともあり、見込み量を大幅に下回っています。」とある。市内事業所の確保が課題。一般就労移行支援に力を入れてほしい。
市の考え方
各事業所、他関係機関との連携・協力を行い、一般就労の促進を行っていきます。
表記について
意見の趣旨
- 「取り組む必要があります。」を「「取り組みが必要です。」に修正(計画案36ページ2行目)
- グラフ表の〈複数回答〉の文字が画面で切れている(計画案37、38、39ページ)
- 「それぞれの役割を検討しつつ、」を「それぞれの役割を検討しながら、」に修正(計画案60ページ「地域のネットワークの強化」1行目)
市の考え方
ご意見のとおり、分かりやすく、見やすい表記に修正します。
その他の意見(1)
意見の趣旨
- プラン案にも記載があるが、障がい分野にかかわらず、他機関との連携を強化し、本プランを良い方向に進めて欲しい。
- 「地域福祉計画・地域福祉活動計画」とすり合わせながら、本計画案を実行して欲しい。
市の考え方
ご意見のとおり、他関係機関との連携・協力を行い、また、地域福祉計画なども踏まえながら、本計画を進めていきたいと考えています。
その他の意見(2)
意見の趣旨
重度知的障がい者(支援区分6)の母。
さまざまな福祉支援を受けながら、現在は家庭で親子二人で生活している。一番心配なのが将来のことで、親なきあとは施設かグループホームで暮らすしかなく、少しずつ探してはいる。
政府の方針では、地域で暮らすためにグループホームへの移行が言われているが、市内では重度障がい者の受け入れは困難。施設も空きがなく、少し遠方まで問い合わせてもなかなか厳しい状況。重度障がい者の支援を市内で安心して受け入れてもらえる所があれば、どれほど助かるか、切に望むところです。
市の考え方
ご意見につきましては、障がいのある人の高齢化や、障がいの重度化などに伴う多様なニーズに対応できるグループホームなど住環境の整備を行い、障がいのある人の生活を、地域全体で支えるサービス提供体制を構築していきたいと考えています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ